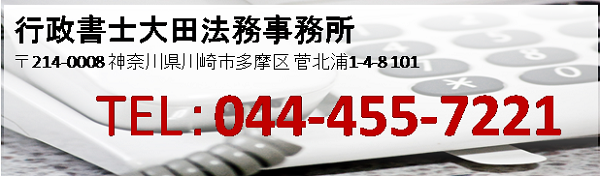戸籍の取り方
家系図調査の基本はまず戸籍・除籍の取得です。戸籍・除籍については必ず全部事項証明書(謄本)を取得します。ときおり「自分は戸籍がいろいろ変って、調べるのが大変だ」という方がいらっしゃいます。
しかし実際に戸籍を取得すると住所地だけが動いていて、戸籍はまったく動いていないという方がほとんどです。
戸籍というものはそうそう簡単には動かすことのないものですので、たいていは住民票を取得して本籍地を確認すればスムースに作業が進みます。戸籍を取得する費用ですが、直接窓口に出向いていけば一通につき750円の手数料のみです。最近は役所でも家系図作成で戸籍を取得する方が増えたためか、「家系図を作成したいので関係ありそうな戸籍をとりたい」と伝えれば、丁寧に対応してくれます。
戸籍の郵送請求
本籍地が遠くて直接役所に取りにいけない場合、郵送での請求になるのですが、少々手間と費用がかかります。
まず手数料は「定額小為替」というものでの支払いを求められますが、これは近くの郵便局までいき(小さいところで取り扱っていない場合もあるようです)1通につき100円の手数料を払って受け取らなくてはなりません。
さらに郵送請求では送るときの郵便代に加え、返送用の封筒と切手の貼り付けも求められますので、
あわせて1000円前後の費用がかかります。
そして時間もかかります。定額小為替や郵送書類を集めて送ってから2日ほどかけて当該の役所に届きます。その役所ですぐに処理してくれればいいのですが、たいていは2、3日かかります。さらに返送にも2日ほどかかります。その間土日が入れば当然役所が休みなので、作業しません。結局は手元に届くまで10日くらいはかかることになります。家系図調査の場合、調査で新たにわかった方の戸籍も同様に取得していきますので、1か月や2か月はすぐにかかってしまうことになります。
戸籍の読み方
さて、届いた戸籍・除籍の全部事項証明書(謄本)をどう読むかです。
まず、世帯主(戸主)があります。この方が戸籍の代表者です。結婚等で新たに戸籍を作られた方であれば、ご自身かご主人がこの世帯主の欄に記載されています。その次が妻・そして子となります。そして世帯主や妻のところの横に小さく「父・母」という欄があります。これがご両親の名前です。
そして縦書きの場合はその上に、横書きの場合は名前の下の所に小さな字でいろいろと書いてあります。「○年○月○日 ○○○地籍より転籍」または「○年○月○日死亡により除籍」などと書かれています。その方がいつ、どこからこの戸籍に入ったか、あるいはいつ亡くなられたかなどの情報です。つまりその方が現在の戸籍に入る前にはどこの戸籍にいたのか、いつ出生の届けがだされたのか、またいつ死亡の届けが誰によって出されたのかといったことです。このデータは家系図づくりにおいて非常に重要なデータです。
ここまでは最近の戸籍についてですので文字もワープロ文字で読みやすく、書いてある内容も一家族のものがほとんどなのでさほど難しくはありません。少し時間をかければ誰でもわかるところです。
ところが改正される前の戸籍、おそらく祖父母あたりの戸籍となると話が違ってきます。
改正前の戸籍
実は戸籍に関する法律(戸籍法)は明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年にそれぞれ法改正があって、その都度それまでの戸籍を改正原戸籍として、新しい戸籍を編纂しています。つまりその都度新しい戸籍ができているわけですが、とりわけ大きな変化があったのが昭和23年の改正です。
(実際に各市町村で戸籍が変わったのは昭和30年代のものが多いようです。)
昭和23年の戸籍法の改正ではこれまで“家”単位で記載されていた戸籍の内容が夫婦とその子供を一つの単位とした家族に代わりました。その結果、それまではひとつの家ということで、戸主を子供に譲った両親や兄弟、孫まで記載されていたものがなくなりました。
戸籍が読めない?
戸籍法の改正によって戸籍の形式が変化した話とは別に、戸籍の解読で挫折される方が多いのには理由があります。そのひとつがコンピュータ化される前の手書きの戸籍です。
戸籍は平成6年の法改正以降、今後変更の可能性のある戸籍はワープロ書きに変更されてきているのですが、残念ながらすでに除籍になって変化しないものについては従来の手書きのものなのです。取り寄せてみた方はおわかりかと思いますが、これは各市町村役場の担当者が墨を使って手書きで記入していますので、字の大きさ、癖、読みやすさ、すべてが千差万別です。達筆の方が多いのか流麗な文字なのですが、流れすぎていて文字がわからなくなったものも数多く見受けます(中にはきれいに整った文字もあります)
また、手元に届くのはコピーですので、中には汚れがひどかったり、字がつぶれてしまっているものもあります。私が以前取得した戸籍では文字が小さすぎる上に何度かコピーを繰り返したかのように字がつぶれてしまっており、まず解読以前に何が書かれているのかすらわからず読めないというものがありました。私どもは仕事ですのでなんとか解読しようとがんばりますし、慣れてくると案外推測できたり、特に必要のない文字だということがわかったりすることもあるのですが、初見の方はおそらくこういった読めない戸籍をみたところで挫折してしまうことも多いと思われます。
読めない文字
幸いにして先にあげたような、まず読み取る上での不都合がなかったとして、次におそらくぶつかるのは文字の問題です。たとえばいきなり誕生日が「○年○月廿日」と書かれてあったりします。(これはわかるかもしれません)広島県に廿日市市(「はつかいちし」)という市がありますので「廿日」→「はつか」=20日ですね。
ほかにも壱日(ついたち)、弐日(ふつか)など漢数字を用いています。
そしてもっとも難しいと思われるのが、変体仮名といわれる仮名文字です。
特に女性の名前に使われていることが多いのですが、漢字を崩して作った文字のため、見た目は「よ」のような文字が読みは「に」だったり、「そ」のように見える文字が読みは「は」だったりします。こうした文字の解読は慣れるとある程度の目途がつけられますし、読めたときは楽しいのですが、なかなか該当する文字が見つからないなど厳しいところもあります。
このように家系図の作成は、戸籍・除籍全部事項証明書を直接役場に出向いて取得したり、郵便で取り寄せる手間もなかなか大変ですし、その後の解読、整理といった作業はなかなかの労力と集中力が必要になります。戸籍は集めてみたけれど、読みづらくて解読できない。あるいは忙しくてじっくり読んでいる余裕がないまま何か月もたってしまった、などということにもなりかねません。外注していただければ通常は2か月程度、ややこしいものでも3〜4か月程度で完成しますし、戸籍の解読や整理といったわずらわしい作業からも解放されたうえで、綺麗に整ったものを手にすることができます。