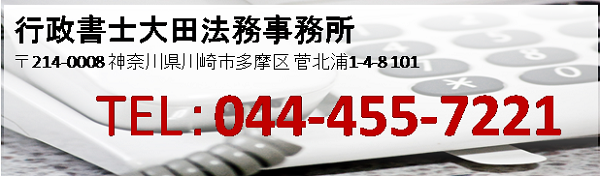家系図とは

家系図というと、旧家の倉庫の奥に眠っている古めかしい古文書のような巻物、あるいは紙綴りを閉じた古書のようなもの想像されるかもしれません。
しかし、家系は旧家や名門と言われる家だけのものではなく、実はどなたでも両親から祖父母、曾祖父母・・・と何代も過去に遡って続く系譜を知り、我が家の歴史を知ることが可能です。
家系図には様々な種類がありますが、自分自身から始まり、2人の両親、次に4人の祖父母、8人の曾祖父母と代を遡るにつれてどんどん関係する人が増えていきます。その一人一人がご自身と同じように一生を生きて今に至るわけです。
家系図を作り、記された先祖の生年月日を歴史の年表と照らし合わせれば、ご先祖がどのような時代を生き、そして今につながっているのかに思いをはせることができます。
幕末の激動の時代に生まれたご先祖、関東大震災の被害にあった高祖父母、あるいは太平洋戦争の時代を生き抜いて巡り合い、結婚して子供を設けた曾祖父母。それぞれどのように変遷の大きな時代を生き抜いてきたのだろうか?と家系図を見ていると様々な想像が生まれ、そしてご先祖への思いが強まります。
家系図づくりのメリットはまさに自分が生まれた経緯を知り、ご先祖を知ることで、自分のルーツを知り、同時にご先祖への感謝の気持ちを持つことができることにあるといえます。
家系図調査は一刻も早く行うべきです。
家系図調査の第一歩はご先祖の除籍謄本の取得にあります。
現在の戸籍につながるものは明治5年から作成されていますが、その戸籍に記載されている人が死亡や婚姻・養子縁組などの理由によって、その戸籍から除かれ記載された人がすべていなくなってしまうとその戸籍は除籍という扱いになります。その除籍の保存期間は平成22年6月に150年に延長されましたが、それ以前は80年でした。つまり古い除籍謄本は廃棄される可能性があるのです。
役所によっては特に整理の必要や機会がなく、80年を超えたものも保存していることも多々あります。しかし時期が過ぎたものについては役所に保存の義務がないので、合併による庁舎の移動などの機会に書類などの整理が行われ、廃棄されることが多くなっています。また自然災害や火災などの予期せぬ出来事によって関係する書類がすべてなくなってしまうこともあります。(実際に火災で失われてしまったケースがありましたす)
明治以前には住民はほとんど本籍地から動かなかったのですが、近年は交通手段の発達で活動区域が大幅に広がっていて曾祖父母の方以前の除籍謄本がなくなってしまうと、そもそもルーツのもととなる出身地を知ることが難しくもなります。思い立ったらすぐに活動を始めることが家系図づくりの第一歩です。